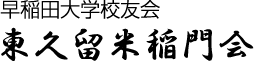臨時開催 第3回ウォーキング(H31.3.13)高尾梅郷、木下沢(こげさわ)梅林 活動報告
-
寒さで引き籠って過ごした冬が去り、待ち望んだ春が一気に訪れたかのような陽光が降り注ぐ快晴の下、総勢10名(男8、女2)で出立。グルメの会との重なりを避けて、開催日を水曜日に振り替えた結果が好天を呼び込んだ一方、参加者が少し寂しいことになったようだ。JR高尾駅から、4.5kmにわたり点在する梅の郷を、片道2時間ほど、ゆったりとして梅見するウォーキングを開始した。(木下沢梅園迄のバスもあるが、今回は利用せず)
木下沢(こげさわ)梅林へと続く高尾梅郷は、初耳という人が多いようだが、知る人ぞ知る梅見の里だ。関東三大梅林には諸説あるが、ほぼ定説となっている越生(おごせ)梅林(H29.2.27ウォーキング実施)と水戸市の偕楽園の二つのほか、三つめとして、小田原市の曽我梅林、安中市の秋間梅林、熱海梅林が挙げられている。関東ナンバーワンの梅林だった青梅の吉野梅郷が、2014年にプラム・ポックス・ウィルス病のため全伐採となってしまうという悲しいニュースがあったが、高尾ではもともと旧甲州街道沿いに点在していた梅をボリュームアップするかたちで1960年代から植樹を始めて梅郷を造ってきた。私見だが、高尾梅郷・木下沢梅林が三大梅林に名を連ねる日も近いと思われる。
歩き始めて15分程後には、現実を離れた別世界に入り、小仏川の堤に植生された「遊歩道梅林」の白い花の屋根の中を歩いていた。ここを抜けて、小仏川に沿った旧甲州街道を跨いで、駒木野の関所跡地にある「関所梅林」で小休止。再び小仏川を越えて、谷の斜面を埋める「天神梅林」では、梅の香を浴びながら筵を広げて憩う人々の中を縫い、咲き乱れる花の中を泳ぐようにして、花と香を楽しんだ。
この先、「湯の花梅林」を遠くに見て、道に沿って咲く梅の花を愛でながら、旧甲州街道の小仏峠方向への上り坂を約30分、この日の最終目的地、約1,400本もの紅梅・白梅が咲く梅の里「木下沢梅林」に到着。下段の梅、中段の梅、小さな広場を含む上段の梅、3つのゾーンに満開の梅が、その自慢の香と共に出迎えてくれた。
「君ならで誰にか見せん梅の花色をも香をも知る人ぞ知る」 紀貫之(古今集)
こうしたロマンチックな想いに浸るのも、梅見の喜び。そして、澄み渡った青空の下での持参の酒が、花による眼と鼻の保養を加えて、「五臓六腑に染みわたる」とはこのことであったか。昼食のコンビニのお握りに、満漢全席に劣らぬ美味を感じたのも、小生だけではなかったでしょう。東久留米に帰り、恒例の打ち上げで喉を潤した。 東海俊孝記
注:木下沢梅園は、花の咲く3月の特定期間だけ無料開放され、他の期間は閉鎖される。







『甲州街道を歩く』第13回(3月18日)牧之原?台が原?JR富士見駅
-
冬に代わって春の到来を漸く感じられた日、総勢5名(今回は男のみ)は、特急「あずさ」から乗り継いで、甲府駅から6つ目のJR日野春駅(標高615m)に降り立った。駅は八ヶ岳の大崩壊による「韮崎岩屑流(七里岩)」が造った崖の上に位置していることから、凡そ100m下の釜無川に沿った甲州街道の前回最終到達点、牧之原交差点までタクシーで下り、ここを今日の出発点とした。この日の行程は、途中に最寄りの駅が無い為、これまでで最長である20㎞を超え、後半は標高956mの富士見駅(標高差400m超)への登り坂が続くタフなウォーキングである。
コース前半は、抜けるような青空の下、左手に甲斐駒ケ岳が迫り、右手少し遠くには南八ヶ岳が望まれ、併せて100万$の眺望に恵まれた上、旧甲州街道は現在の国道20号線を縫うように走って自動車の往来を避けており、ウォーキングを大いに楽むことが出来た。甲斐駒ヶ岳に源を発し、白州町が世に誇る清流尾白川に掛かる橋の袂にある甲州街道古道入口「はらぢみち碑」から、今に残る小道を辿り「台が原宿」に至る。白州の名水が産んだ江戸時代からの山梨銘醸「七賢」蔵元(近くにサントリー白州工場もある)と旧旅籠の建物を使った信玄餅の老舗「金精軒」を訪れ、各自、それぞれで土地由来の名品を土産として購入した。
JR中央本線は、この辺りから崖下の釜無川に沿って走る国道20号から離れて、七里岩の高台を長坂駅、小渕沢駅と進むが、甲州街道は交通機関を利用するには遠くなった道を、「教来石宿」を経て、下蔦木の国界橋(甲斐と信濃の境、七里岩の北端)迄ひたすらに歩いた。この間歩きに忙しく、残念な事に、「目には青葉山ほととぎす初かつお」の山口素堂の生家と句碑を見落としてしまった。
七里岩と別れると、街道は左右の景観を見渡せない、山あいを走る国道20号の歩道を辿ることになり、自動車騒音と風圧に併せてJR富士見駅に向けての上り坂がかぶさってきた。「蔦木宿」の本陣大阪屋跡のある上蔦木を過ぎると、目ぼしい遺跡等もなく、最終目的地を目指して歩を稼ぐだけとなり、残りの行程を1時間半超、足を棒にしてJR富士見駅に辿り着き、20㎞超の長丁場の実感となった。
汽車の本数が少ない富士見駅から鈍行で小淵沢駅へ、そこで特急に乗り換え、幸いにも乗客の疎らな車内で酒を酌み交わし、疲れた身体を慰めた。東海俊孝記
東稲ニュース No.105 アップしました
-
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ウォーキング(第71回 4月1日 ) 幸手(さって)権現堂桜堤
-
ウォーキング(第71回) 幸手(さって)権現堂桜堤(桜と菜の花を鑑賞)
日時:4月1日(月) *雨天の場合:順延又は中止(協議する)
集合: 8 : 50 東久留米駅改札口 ☆途中駅での参加の方は事前に連絡を!
交通:<往路>
東久留米 9:02発 →(武蔵野線)新秋津9:17発 →南越谷9:49着 徒歩 →
→(東武伊勢崎線)新越谷10:01発(日光線南栗橋行急行)→幸手着10:28
行程:今回のウォーキングの負荷は軽いので、気軽にご参加下さい。
幸手駅から幸手権現堂桜堤まで:2㎞(徒歩30分)*バスも利用可
★地面に敷く物(ブルーシート等)、紙コップがあれば、ご持参下さい。
費用: 参加費300円
交通費(西武池袋線144 + JR550 + 東武360)× 2 = 合計2,108円
桜祭り:期間3月25日(月)~4月9日(火)
長さ1kmにわたる堤に約1,000本のソメイヨシノが咲き誇り桜のトンネルを作る。また、堤の隣には、菜の花が作付けされ、桜の淡いピンクと菜の花の黄色とのコントラストが見事である。
桜祭りの期間中は、約100店舗の露店が出店し、様々なイベントが行わる。
連絡先:東海俊孝 電話473 ? 8566(携帯: 080 ? 1205 ? 9494)
e-mail toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp
別処尚志 電話475 – 1710 e-mail t_bessyo@jcom.zaq.ne.jp
以上
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ウォーキング(臨時第3回、3月14日(水))高尾の梅郷を散策
-
ウォーキング(臨時第3回)高尾の梅郷を散策、木下沢(こげさわ)梅林が最終目的地
日時:3月14日(水)集合8 : 45 a.m. 東久留米駅改札口
*悪天候の場合:中止か順延か、追って協議。
**歩行の負荷は軽度。バス利用で殆ど歩かないことも出来る。
<行程> ★途中駅からご参加の方は、事前にご連絡下さい
(鈍行所沢行) 乗り換え 乗り換え
東久留米発8:52 →新秋津発9:08→西国分寺、(高尾行)→ 高尾
9:17着 9:30発 9:53着
●高尾駅からは原則歩きだが、木下梅園までバス利用も可
費用: 参加費無し(今回は下見なしの為)、交通費合計 1,216円* と飲食代
*交通費内訳 東久留米─秋津 144円×2 新秋津─高尾 464円×2
昼食: 弁当持参が無難と思われる
連絡先:東海俊孝 電話473 – 8566 e-mail toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp
携帯:080 – 1205 – 9494
別処尚志 電話475 – 1710 e-mail t_bessyo@jcom.zaq.ne.jp